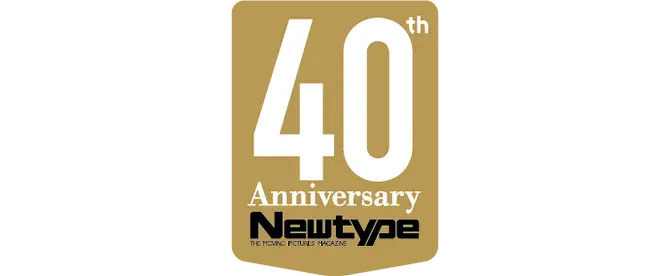新作&おすすめアニメのすべてがわかる!
「月刊ニュータイプ」公式サイト
万城目学&野島一人「メタルギア」対談[その3]
■■対談中にゲーム本編および、小説版のネタバレが入ります■■
野島:小島監督のツイートに“「V」は運命に縛られたスネークを解放し、そしてスネークに縛られたプレイヤー自らがバトンを引継ぐ事で伝説の円環を完成させるものです。その訣別は決して幻肢痛ではなく、さらに前に進む為の埋まらない「永遠の空白」となるはず”という発言がありました。このあとに個人的にメールをいただいたのですが、そこにはこんな内容のことが記されていました。
初期のビデオ・ゲームには物語がなかったけれど、「メタルギア」はそこに物語を付け加えた。主人公のスネークをプレイヤーが操作することで一緒に物語をつくってきた。その後、シリーズが続くことによってプレイヤーはソリッド・スネークやネイキッド・スネークになってメタルギア・サーガという伝説をつくってきました。最後の「メタルギア」は、主人公であるスネークをプレイヤーに返すしかない。今後の物語は自分でつくる。円環をつなぐ、完成させる、というのはこういうことだ、と。これが映画のように一方通行のメディアだったら、「V」のラストのようなことは不可能だったけれど、ゲームだからこそできたことだ、と。今まで一緒につくってきた物語をユーザーに返す。それが「V」の本当の意図だった。
「V」でユーザーが影武者にならなければ、その後のビッグボスは殺されてしまっていた。しかも、「V」以前に、最初の「メタルギア」でソリッド・スネークになったユーザーは、ビッグボスをすでに殺しているんです。だから最後の作品では、もう一度、ユーザーが物語の中に入って、自らの手で円環を閉じる。そうしてはじめて物語はユーザーのものになるんだということなんだと思うのです。映画にも小説にもできない、ゲームというメディアだからこそできる「ユーザーと一緒に物語を創る」という、「メタルギア」が当初からやってきたことの集大成こそが今回の「V」なんじゃないか。
万城目:みんながそこまで理解するには、もう少し時間がかかるんじゃないですかね。みんなのビッグボスやスネークへの思い入れが強いのは当然なので、それがほどけたころにようやく理解できるんじゃないかなあ。あらかじめ決められたストーリーどおりに進んでいくという思いこみがあるから、突然、ゲーム画面から問いかけられると、バトンを渡されると、自分で処理できなくなるんですよね。そういうゲーム体験を、僕も含めてしたことがないから。「MGS2」でバトンがスネークから雷電に渡っただけでも、それほどの拒否反応があったなら、今回はそれ以上のものあっても仕方がないかもしれない。何せ、渡される先が自分ですから。
野島:「MGS」ではストーリーに分岐がありましたが、「MGS2」ではストーリーの根幹にかかわる設定として分岐を排除していますね。それ以降のシリーズでも分岐はない。「MGS2」では最後のほうでスネークが雷電に「たしかに今回、おまえが自分から何かを選ぶことはなかったかもしれん。だが、その間におまえが考えたこと、おまえが感じたことは、おまえ自身のものだ」と言っています。これも「V」と同じ構造ですよね。あらかじめ定められたルートのとおりに進めていくと、ゲーム側から問いかけられる。ここまで来たのはプレイヤー自身であって、そこで感じたものはプレイヤー自身のものだ。そこから先は自分で考えていいんだ、という。それこそが監督からのメッセージであり、MGSが他のゲームと違う最大の特徴です。ユーザーをキャラクターに没入させて、それこそが自分だったんだ、と返せる仕掛けって、映画や小説ではなかなか難しいと思うんです。これこそゲームならではっていうか。
万城目:小説だとキャラクターを操作させることはできないですもんね。それは根本的に小説では無理だと思う。
野島:さきほど万城目さんは「理解するにはもう少し時間がかかる」とおっしゃいましたが、「MGS2」が発表された直後も非難がけっこうあって、まだ作家になる前の伊藤計劃さんがいわば最前線に立って「こんなゲームを喜ぶのは俺だけだ!」と絶賛していたんです。
万城目:そうだったんですね。
野島:実はこの当時から僕も小島さんとは交流があったんですが、伊藤さんほどにはゲームの本質を理解できていませんでした。あの複雑なストーリーや、小島さんが投げかけたメッセージをわかっていたのは伊藤さんだった。おそらく彼は、その後もずっと「MGS2」のことを考えつづけていたんだと思うんです。S3計画が本当に意味するのは何か、自由意志とは何か、物語るということは何か、ということを考えに考えた末に、「虐殺器官」と「ハーモニー」が生まれたんだ、と僕は解釈しています。「MGS2」って、お話としてはきれいに終わってないですよね。リキッド=オセロットの行方もわからないし。
万城目:それぞれのキャラのエピソードもそうですが、やっぱり言いようのない、現実の底が抜けるような恐怖感を残しますよね。
野島:そのゲームから受けた「終わらない」感覚の本質を、伊藤さんはしつこく考えた。それで得た答えのひとつが「虐殺器官」であり、もうひとつが「ハーモニー」だったとしか僕には思えないんですね。今回の「V」の解説で小島監督が「空白があるから先に進める。この空白こそが「V」なのだ」と書いていますが、「MGS2」がそれぞれのユーザーに残した空白を埋めたのが伊藤計劃だったんじゃないかと。【対談その4に続く】
■万城目学(まきめまなぶ)
1976年大阪府生まれ。京都大学法学部卒業。2006年、第4回ボイルドエッグズ新人賞を受賞した「鴨川ホルモー」でデビュー。「鹿男あをによし」「プリンセス・トヨトミ」「偉大なる、しゅららぼん」など、多くの作品が映像化されている。最近作に「とっぴんぱらりの風太郎」「悟浄出立
」。文芸カドカワで「バベル九朔」連載中。
また、「メタルギア」シリーズの大ファンでもあり、小島監督とも交流がある。
「MGS V」についてのインタビューはwebサイト「シネマトゥデイ」の以下のページにも。http://www.cinematoday.jp/page/A0004677
■野島一人(のじまひとり)
蛇年。小島監督ではない。「メタルギアソリッド」のノベライズを手がける。