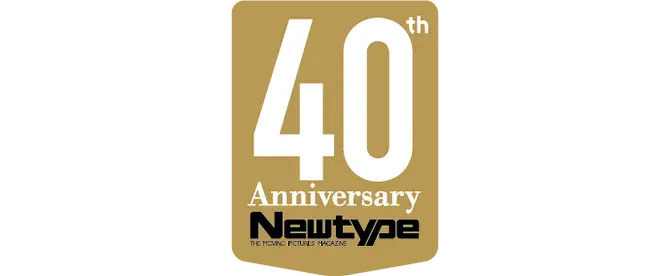新作&おすすめアニメのすべてがわかる!
「月刊ニュータイプ」公式サイト
「彼方のアストラ」音響監督・飯田里樹×音響効果・奥田維城インタビュー「明るく前向きな作品だからこそ、コメディタッチの音を大切にした」
TVアニメ「彼方のアストラ」を盛り上げるためのキャスト&スタッフによるリレー連載。第12回のゲストは、音響監督の飯田里樹さんと音響効果の奥田維城さんです。環境音や効果音の制作秘話を中心に、作品世界を彩る音の演出についてうかがいました。
――今回、お二人がこの作品に参加された簡単な経緯を教えていただけますでしょうか。
飯田 私はLercheさんから音響監督の依頼をいただきました。音響効果をどなたにするかという話になったときに、「彼方のアストラ」は未知の惑星が舞台で環境も星々によって違う、その上いろんな生物が出てくる作品なので、SFの造詣が深い方にお願いしたいと思ったんです。監督の安藤(正臣)さんも映画をよく観ている方で、「インターステラー」や「ゼロ・グラビティ」をイメージしていると伺ったので、音響効果の方も映画に詳しい方がいいだろうと考え、奥田さんにお願いすることになりました。
奥田 実は、僕らって同い年でキャリアもほぼ同じタイミングでスタートしているんです。長いこと一緒にやってきていますし、音の演出がお互いに想像しやすく意見も出しやすいので、すごく楽しみでしたね。
――音の方向性について、安藤監督とはどのようなお打ち合わせをされたのでしょうか。
飯田 安藤監督から最初に伝えられたのは、「この作品の魅力は明るく前向きなキャラクターにある」ということでした。「見終わったあとに視聴者が元気になるアニメをつくりたい」とのことだったので、そこは大事にしたいなと。
奥田 会話劇がメインのヒューマンドラマということですよね。音響効果としては会話を邪魔するような効果音はつけないようにしようと思いました。
飯田 ただ、キャラクターの心情や生い立ち、人間関係などのドラマを色濃くしていくと、SF要素や惑星の生態系の話はどうしても縮小せざるを得なくなってしまうんです。なので、そこは効果音などでフォローすることにしました。
奥田 とはいえ、生態系に関してはそれほどたくさん音を入れたという印象はなかったですね。
飯田 ドラポンやグルッピーなどは声優さんに声を当ててもらっていましたからね。なにせ、鳴き声が「グルッピー」なので。
奥田 むしろ大変だったのは宇宙の音だったかなと。
――宇宙の音はどのようにつくっていったのでしょうか。
奥田 荒野に流れるような音とはまた違った「ゴォォォ」という音をしっかり出したかったので、複数の音を足して強調するようにしました。宇宙って、空間は広いけれど密室なんです。その圧迫感に晒されていること表現するために、宇宙が見えたときはできるだけその音を出すようにしています。
同じようにカナタたちの親が登場するシーンも低めの音で統一しました。本当に怖い物はなんなのか音で明確にわかったらいいなと思い、宇宙の密室感や親の圧のようなカナタたちを追い詰める要素に対してはそういう音付けをするようにしています。逆に、惑星で流れる風の音などは軽くするようにしました。
――宇宙は広いけど密室というのがすごく面白いなと思いました。
飯田 音作りという意味でもそうですが、実は内容としても情報が入ってこない中で推理を進めていくというクローズドサークルの話ですからね。
――第1話冒頭でアリエスが宇宙空間に投げ出されたとき、心臓の音が入っていますがあれは音楽ですか。
奥田 音楽ですね。
飯田 最初は心臓の音を効果音として入れていたんですが、音楽と音が被ってしまって。
奥田 それに音楽のほうが正確にリズムを刻めて無言の圧迫感が出せるということで、音楽のみにしようとなったんです。
――横山克さんと信澤宣明さんの音楽についてはいかがでしたか?
飯田 Lercheの比嘉(勇二)プロデューサーが横山さんを推薦してくださって、横山さんにお願いすることになりました。驚いたのは最初の打ち合わせの段階でイメージ曲を書いてきてくださったことですね。しかも、大変素晴らしいものだったんです。ただ、かなり壮大でシリアスな曲だったので、念のため、コミカルシーンの曲や若者たちの日常を表現した普段使いの曲も必要なのでバランスはとってほしい、とお伝えしました。
奥田 立派すぎるくらい立派な曲でしたね。
飯田 劇場版かというくらいのクォリティでした。
――リズムを重視した曲も多いですよね。
飯田 推理シーンで使うようなミステリー感のある曲をたくさんお願いしておいたんです。そこに横山さんたちがSF感や宇宙感を加えてくださって、作品にマッチしたバランスのいい曲になりました。
奥田 分厚い音が多くて、効果音とのバランスも取りやすかったですね。SF作品って現実にはない音作りをするので、わかりやすいシンセサイザーの音だとどうしても被ってしまうんです。お互いが馴染み過ぎると、どちらも聞こえにくくなるというデメリットがあるんですが、分厚い音を使った音楽だったので、効果音が音楽の邪魔をすることもなかったですね。
飯田 また、本作は会話シーンが多いのでベースに流す音楽も重要になるんですが、曲の主張が強すぎると視聴者がセリフに集中できなくなるんです。そういうシーン用にシリアスだけど静かに雰囲気を演出してくれる曲をいくつか発注しておいたのですが、丁寧につくってくださって。とてもありがたかったです。
――一方で、ギャグシーンではコメディタッチの効果音がたくさんついています。
飯田 原作も「バーン」とか「ドーン」とかたくさん描いてありますし、前後にシリアスな展開があるからといってコミック音を避けてしまっては篠原(健太)先生の味が出なくなってしまう。そこで、コメディタッチの音は可能な限りつけるようにました。ただ、やりすぎるとどうしても浮いてしまうんですよね。
奥田 調整は難航しましたよね。
飯田 特に惑星アリスペードのとき(第5話)がそうでしたね。B5班のパートは和気あいあいとした雰囲気で進行していくので、そのぶんコメディシーンもたくさん入ります。ただサバイバル中ではあるので、ギャグ音を入れすぎるとやりすぎじゃないか、でも水着回だから楽しい雰囲気も欲しいし……といろんな意見が出てきて……。
奥田 でも、この作品の特徴は明るく旅をするということですから、楽しい方向に調整したいという思いはありましたね。それに中盤以降は話がどんどん重たくなっていくので、どうしても先に明るく楽しい旅だという色づけをしておきたかったんです。
飯田 篠原先生からもキャンプ感や修学旅行感は出してほしいとリクエストをいただきましたしね。命の危機はあるけれど決してつらいだけの旅ではないことは、音でも強調しておきたいなと。
奥田 普通の漂流ものだったらみんな精神が参り、疑心暗鬼になりながらも、それを乗り越えていくという流れになるかと思うんですが、「彼方のアストラ」はそうではないですから。刺客の存在はありながらも、苦痛を感じるのではなく楽しく困難を乗り越えようとする話なので。画とのバランスを見ながら、なるべく楽しい雰囲気を出すようにしました。
――画とのバランスも重要なんですね。
飯田 そうですね。ギャグシーンは画もカメラワークとかで「バーン」とか「びょーん」とか、そういう雰囲気を出しているので、我々もついその音を乗せてしまいそうになるんですが、そこは画に譲るようにしました。画ですでにギャグを表現しているカットに音でギャグを盛ってしまうと味付けが濃すぎてしまう。逆に会話シーンに挟まれるさりげないボケにコミック音を足したりする場面もありました。
――この先、注目してほしいポイントはどんなところでしょうか?
飯田 これからは種明かしのフェイズになり、会話が中心になっていきますので、ぜひ演者のお芝居に注目していただきたいですね。特に第11話の中心となるであろうシャルス役の島﨑(信長)さん。シャルスが内包する様々な面を多彩に表現したお芝居が聞けると思います。
奥田 この作品ですごくいいなと思ったのは、カナタたちとその親の生き方の対比です。子どもたちはどんなに挫折しそうになってもずっと前を向いて進んできたのに対し、大人たちは自分の生命が終わることに悲観的で、死というものを恐れるあまり、いわば時間を巻き戻そうとしました。この対比があったことで、カナタたちのめげない心がより強調されることになったと思うので、この先もカナタたちの生き様に注目してほしいですね。
【取材・文:岩倉大輔】
放送:AT-X…毎週水曜21:00~ ※リピート放送あり
TOKYO MX…毎週水曜25:05~
テレビ愛知…毎週水曜26:35~
KBS京都…毎週水曜25:05~
サンテレビ…毎週水曜25:30~
BS11…毎週水曜25:30~
配信:dアニメストア、Amazon Prime Video…毎週水曜21:30 他
■「彼方のアストラ」Blu-ray/DVD BOX 上巻(第1話~第6話)
発売日:2019年10月25日
価格:Blu-ray税別1万8000円、 DVD税別1万6000円
【初回生産特典】
1:スペシャルアウターケース
2:キャラクターデザイン・黒澤桂子描き下ろしデジパック
3:B5班キャンプ日誌
4:原画集
5:スペシャルソングCD Vol.1
【毎回特典】
1:スペシャルWEB予告
2:ノンクレジットOP・ED
3:キャストオーディオコメンタリー
■「彼方のアストラ」Blu-ray/DVD BOX 下巻(第7話~第12話)
発売日:2019年12月25日
価格:Blu-ray税別1万8000円、 DVD税別1万6000円
【初回生産特典】
1:スペシャルアウターケース
2:キャラクターデザイン・黒澤桂子描き下ろしデジパック
3:B5班キャンプ日誌
4:原画集
5:スペシャルソングCD Vol.2
【毎回特典】
1:スペシャルWEB予告
2:キャストオーディオコメンタリー
3:PV・CM集
リンク:TVアニメ「彼方のアストラ」公式サイト
公式Twitter・@astra_anime