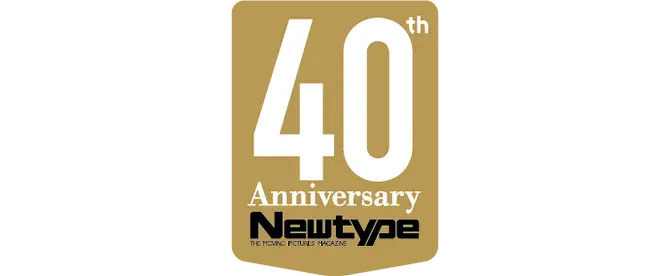新作&おすすめアニメのすべてがわかる!
「月刊ニュータイプ」公式サイト
今はベストパートナーになれていると感じます―TVアニメ「ドロヘドロ」高木渉&近藤玲奈インタビュー
2000年から18年にわたって連載された林田球さんの人気コミック「ドロヘドロ」。魔法によって顔をトカゲにされてしまった記憶喪失の男カイマンが、相棒のニカイドウと共に自分に魔法をかけた魔法使いを探す物語です。グロテスクかと思えばコミカル、ダークかと思えばポップ……独特な世界設定とキャラクターたちが紡ぐ物語は、多くの人を虜にしてきました。
そのTVアニメが、2020年1月12日(日)からTOKYO MX、BS11他で放送開始となります。キャスト陣は「おいでませ、混沌」と銘打たれた本作とどのように向き合い、どう演じているのでしょうか? カイマン役の高木渉さんと、ニカイドウ役の近藤玲奈さんへのインタビューをお届けします。
――作品に触れたときの第一印象を教えてください。
高木 「すごくダークで、グロテスク!」というのが第一印象でした(笑)。オーディションを受けて主人公のカイマン役に決まった時は「やったー!」と思うと同時に、大勢のコアなファンのみなさんの期待に応えられるだろうか? と自問もしました。でもその後、原作の林田(球)先生もオーディションで僕を推してくださったと知って、とても嬉しく、背中を押されているような心強さを感じました。
近藤 オーディションの話をいただいたのがきっかけで原作を拝読させていただきましたが、キャラクターのインパクトがものすごく強くて驚きました。それぞれが、独特で個性的。読み進めていくうちに明らかになる真実もあって、惹き込まれました。ニカイドウはパワフルで元気な女の子で、今までやったことがないキャラクターだなと思いながら、楽しんで自然体で演じてみました。
――それぞれが演じるカイマンとニカイドウの特徴や魅力を教えてください。
高木 カイマンは暴力的なところもありながら、心優しいところやコミカルな一面も持つ人物です。いかついトカゲの顔とニカイドウという可愛さとのギャップも魅力のひとつですね。一方、ナレーションやモノローグでは静かなタッチで芝居をしていますので、このトカゲの顔の下の素顔はどのようなものなのだろうと想像させてくれる一面もあります。バリエーションのある芝居を要求される、役者冥利に尽きるキャラクターです。
――カイマンは口の中に謎の男がいるなど、ミステリアスさも持っていますね。
高木 物語開始時点のカイマンは記憶喪失で口の中の男に関して何も分かっていませんので、芝居もそれに徹しています。長い作品ですから、アニメで初めて「ドロヘドロ」をご覧になるみなさんも一緒に楽しんでいってください。カイマンを演じるうえでニカイドウとのコンビネーションはとても大事になってくるのですが、第1話のアフレコのときはまだお互い探り合っている感じもあってね。逆にそれがまた良い緊張感にもなりましたが、話数を重ねるごとに玲奈ちゃんの芝居に力強さが出てきて、どんどんキャッチボールが楽しくなっていきました。今はベストパートナーになっていると思いますよ。(近藤さんを見ると)かわいらしくて、奥ゆかしい感じがするでしょう? でも、それだけではなくてすごく芯が強い人なんですよ。だから、芝居もグイグイくるんです。
近藤 それは高木さんが受け入れてくださるからですよ! 最初のうちは「先輩方にしっかりついていかなくちゃ」という気持ちばかりが先立って緊張でガチガチでしたが、今は林(祐一郎)監督からも「2人のコンビネーションがよくなってきたね」と言っていただけるようになりました。ニカイドウはカイマンと話しているときは明るく快活ですが、1人でいるときは真剣な表情を見せたり、戦うときは凛々しさを見せたりします。原作を拝読していても頼り甲斐や安心感があるキャラクターだと感じましたので、そんな彼女の強さをお芝居で表現できるよう、意識しました。
――ダークで、ポップで、コミカルで、グロテスク……。「ドロヘドロ」という作品はいろいろな顔を持っていると思いますが、そんな本作と向き合ううえでどのようなことに気を使われましたか。
高木 本当にその通りで、こういう世界観ってなかなかないですよね。「ドロヘドロ」というタイトルからしてもね。だからこそ、ファンの方たちは本作にさまざまなイメージを持っておられると思うので、それにマッチできるかという不安はありました。もちろん、ただ合わせるわけではなく、自分で考えたうえでこれがベストだと思える芝居で臨みますが、僕らが演じる「ドロヘドロ」がどういう風に受け取られるのか、受け入れてもらえるのかにドキドキしています。
近藤 第1話のアフレコから(他のキャストの)みなさんが個性的なお芝居でアプローチされてたので、想像しきれていなかった世界観がそこで一気に広がりました。その中でニカイドウの立ち位置をしっかり確立するべく、セリフ一つ一つを印象付けられるように必死でしたね。ニカイドウは、客観的に見ていると怖さすら感じさせるときもあったりするので、そこはしっかり意識して「怖がらずに、女の子っぽさをあまり出さずに堂々とやるしかない」とぶつかっていきました。いえ、元々自分が女の子らしいとは思っていないんですけど……(笑)。
高木 いやいや、女の子らしい子ですよ。いっしょに飲んでみれば分かりますけど!
近藤 私、お酒全然飲めませんから!(笑) 最初は自分とはかけ離れているようにすら見えたニカイドウも、向き合っていくと自分の素の部分とつながるところもあってリンクしてきて。すぐに楽しく演じられるようになりました。
高木 それに、玲奈ちゃんはグロテスクな描写がある作品も結構好きなんだよね。
近藤 そうなんです!
高木 玲奈ちゃんのそういう隠れた部分が、ニカイドウの芝居で出てきますよ!
――先ほど写真撮影をさせていただきましたが、和やかでとても明るい雰囲気でした。アフレコ現場の雰囲気もこのような感じなのでしょうか?
近藤 他のキャストの方々は先輩ばかりで最初はドキドキしっぱなしでしたが、高木さんや(堀内)賢雄さんがとてもよくしてくださいまして。その場にいるのが心地よくて楽しい現場です! 高木さんが、なんだか学校の先生みたいなんです(笑)。
高木 ははは(笑)。バカなことばかり言ってるからかな?
近藤 こんな風に、いつも率先してムードーメーカーになって雰囲気作りをしてくださるんです。おかげさまで、いつも次に現場に入れるときが待ち遠しいんです。
高木 そう言ってもらえると嬉しいね! 僕はどの番組でもそうなんだけど、スタジオがしんみりしているのが嫌でね。「現場が楽しく芝居できていれば、絶対いい作品になる」と思ってるんですよ。みんなで笑って空気がほぐれてくれれば、その分、本番では気持ちを切り替えて緊張感も持てるでしょう。そういうメリハリは、いつも心がけています。
――先ほどもお話に挙がりましたが、林監督や藤田(亜紀子)音響監督とはどのような打ち合わせやディレクションをされましたか?
高木 藤田さんは、具体的に分かりやすく演出しながらみんなを引っ張ってくれます。林監督は、口数は少ないけれどいつもみんなを見守ってくれているお父さんって感じ(笑)。絵の疑問に思ったことを聞くときちんと答えや指示をくれます。ブースのキャスト陣とコントロール・ルームのスタッフ陣、みんなが一つになっているという感覚がいいですね。アフレコが始まってすぐに、林田先生やスタッフ、メインキャストでご飯に行けたのもよかったな。
――やはり、カイマンの大好物の餃子を食べたりしたんでしょうか?
近藤 その時は7月で、ちょうど高木さんと賢雄さんのお誕生日が近いということで、ギョーザの形をしたケーキでお二人をお祝いしました!
――ギョーザ型ケーキとは驚きです! 話を戻しますが、現場では林監督がみなさんのお父さんのように見守ってくれているということは、近藤さんから見れば現場に"学校の先生"と"お父さん"がそろい踏みしているような感じなのでしょうか?
近藤 そうですね!(笑) お父さんみたいな方たちがたくさんです! 賢雄さんとは現場で席が隣になることが多いのですが、雑談でリラックスさせてくださったりします。あとは、スタジオにあるリモコンをご自分のスマホだと勘違いして持ち帰ってしまいそうになっていたり……(笑)。
高木 ははは、小ネタ仕込むなぁ〜(笑)。ニカイドウとカイマンは作中でベストパートナーでなくちゃいけないから、僕はスタジオでも第1話のアフレコから玲奈ちゃんの隣に座ろうと思っていたのに、いつの間にか賢雄さんが僕らの間に座ってるんですよ。もう、こんな現場です(笑)。
――今、"ベストパートナー"というお言葉が出ましたが、カイマンとニカイドウの関係性や距離感はどのようにとらえられていますか?
高木 これは難しいね。カイマンとしては記憶を失って倒れていた自分を助けてくれた恩人だし、名前も付けてくれたしで頼りきっていますが、同時に守りたいという気持ちも持っていると思います。でも、恋人ではないし、そこに恋愛感情はきっとないんですよね。少なくともカイマンからは絶対に恋愛っぽいことを言い出さないだろうと思っています。そんなカイマンを演じながら思うのは……「なにがあっても」友達、という感じです。
近藤 原作を拝読したときに、結構切ないところもある2人だと感じました。ニカイドウはカイマンの謎を解くために協力してがんばりますが、そのためには彼女も自分の過去と向き合わなければならないときもあったり、それが原因で2人の距離が離れることもあったりして……。近づくかなと思うたびに何かが起きて、でも離ればなれになっても、お互いに信頼しあっているから大丈夫だろうと信じていられる。そんな2人はやっぱり……「なにがあっても」友達、だと思います。
――綺麗にお答えがそろいましたね! ありがとうございました。
放送:TOKYO MX、BS11…2020年1月12日より毎週日曜24:00~
MBS…2020年1月14日より毎週火曜27:00~
配信:Netflixにて前日先行配信
スタッフ:原作…林田球(小学館「ゲッサン」刊)/監督…林祐一郎/シリーズ構成…瀬古浩司/キャラクターデザイン…岸友洋/世界観設計・美術監督…木村真二/画面設計…淡輪雄介/色彩設計…鷲田知子/3DCGディレクター…野本郁紀/撮影監督…朴孝圭/編集…吉武将人/音響監督…藤田亜紀子/音楽プロデュース…(K)NoW_NAME/アニメーション制作…MAPPA
キャスト:カイマン…高木渉/ニカイドウ…近藤玲奈/煙…堀内賢雄/心…細谷佳正/能井…小林ゆう/藤田…高梨謙吾/恵比寿…富田美憂/バウクス…江川央生/カスカベ…市来光弘/キクラゲ…鵜殿麻由/栗鼠…ソンド/丹波…稲田徹/ターキー…三木眞一郎/アス…郷田ほづみ/鳥太…勝杏里
リンク:TVアニメ「ドロヘドロ」公式サイト
公式Twitter・@dorohedoro_PR